はじめに
私は臨床初期、痛みのことばかりを考え、振り返ると常に「痛いですか?」と尋ねていた。
それが結果として痛みを長引かせていた場合もあったのではないかと今は反省している。
では、なぜその「痛いですか?」という質問をしてはならないのか。
本稿では、臨床でも頻繁に直面するこの論点を扱う。
ただし、本稿が示すのは漫然と反復する”ただの質問”を避けるということであって、痛み評価そのものを否定するものではない。
とくに急性疼痛でADLや基本動作が阻害されている場合は、構造化された痛み評価が最優先の課題である。
一方で、慢性疼痛(あるいはその高リスク)が示唆される場合には、無目的な反復質問が痛みの顕在化や注意の固定化を助長しうるため、質問設計と頻度管理が重要である。
臨床でよくある痛みの質問とは
臨床の場や廊下での移動時などに、以下のやり取りをしばしば耳にするし、私自身も行っていた。
・「痛いですか?」
・「どのような痛みですか?」
・「どこが痛いですか?」
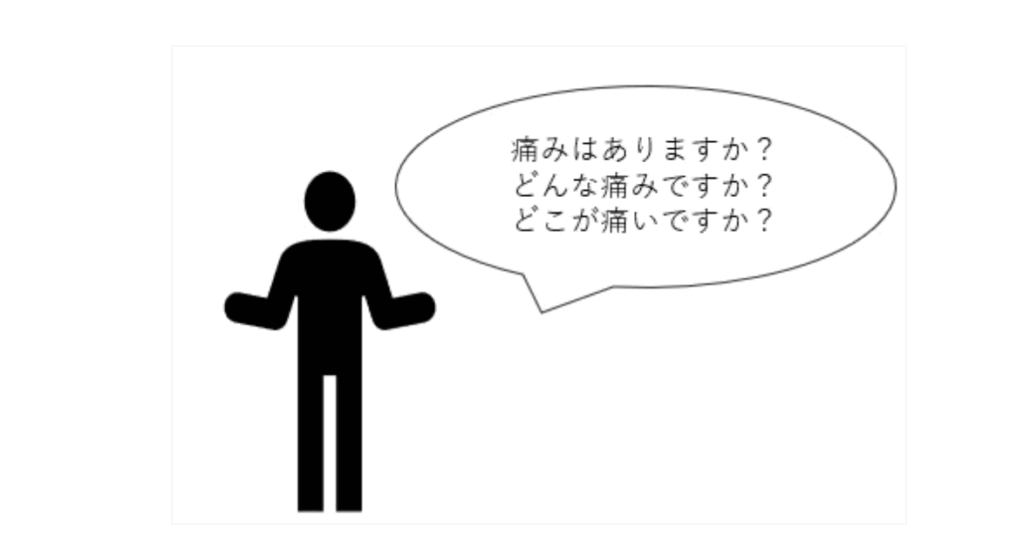
痛みに関する質問をすべて禁じるわけではない(本音としては、可能な限り質問を減らしたいと考える)。
以下のポイントを踏まえ、評価として設計して問うか、問わずに観察で置き換えるかを選ぶべきである。
① タイミング(どこで、誰に)〜特徴はスクリーニングの糸口に過ぎない〜
移動中(とくに歩行中)など活動の最中に、無目的な質問は痛みに注意を固定化しやすいので控える。
ただし、これは特徴ベースの注意喚起であり、決定因ではない。
実際には慢性疼痛の評価(後述)で状態を層別化し、質問の有無・方法・頻度を決めるのが妥当である。
・質問を控える可能性がある特徴
(例):潔癖傾向で説明要求が強い/手術・外傷が初めてで不安が強い/痛み話題で表情が急変する/認知症など。
※いずれも慢性疼痛評価で裏を取ることが前提である。
② 内容—評価目的か、雑談かを常に明確化
「痛いですか?」等を漫然と反復すると、感覚→認知→回避のサイクルを強める可能性がある。
一方、急性期における疼痛評価は優先度が高い。
よって、評価目的・項目・頻度・タイミングをあらかじめ設計し、必要最小限の回数で一貫して記録する。
③ セラピストの意図〜評価ならプロトコル、会話なら転換〜
問診として行うならプロトコル化(例:開始時/負荷変更時/終了時のみ)。
会話の流れで痛みに着地しそうなら、行動・表情・動作観察へ転換する。目的が曖昧な質問は避ける。
④ 説明責任—「原因仮説と見通し」を短く返す
「どこが痛いですか?」で止めず、想定機序・見通し・セルフマネジメントまで短く返す。
説明のない反復質問は不安・恐怖を増幅しやすい。
慢性疼痛の評価(簡便版)
目的:慢性疼痛(または移行リスク)を早期に見極め、質問設計を変える判断材料とする。
実施時期:①導入週、②再評価(2〜4週)、③経過不良時。
・評価枠組み
1.時間軸:3〜6か月の持続・反復。2か月前後の可塑的変化に留意し、2か月以内でも増悪・広がり・回避固定化が強い場合は移行リスクとみなす。
2.痛みの干渉:活動・睡眠・気分・集中への影響(Interference)を簡便に確認。
3.感作・破局化の徴候:破局化の語り、部位拡大、軽微刺激での不快増大、過度の回避。施設運用に応じ、簡易スケール(破局化短版・感作スクリーニング等)の併用を検討。
4.神経障害性の示唆:灼熱感・電撃痛・しびれ優位等(必要時に神経障害性スクリーニング)。
・評価に基づく方針
急性疼痛がADL・基本動作を阻害:構造化した痛み評価を積極的に実施(定点:開始時/負荷変更時/終了時)。
慢性疼痛または高リスク:漫然とした反復質問は避け、観察・機能課題・行動指標を主軸に、質問は目的限定・低頻度で行う。
備考(可塑性)
脳は約2か月で可塑的変化を起こしうる。
入口は急性疼痛であるためまず急性期管理が重要である。
質問が慢性疼痛を必ず招くわけではないが、素因や文脈によって無目的な反復が不利益となる可能性がある。
したがって、評価にもとづく選別と設計が肝要である。
痛みへの悪影響とは何か
悪影響とは、痛みが継続してしまうこと、すなわち慢性痛の形成である。
痛みは末梢受容器から脊髄・脳へ伝達され、一次痛・二次痛がある。
二次痛は大脳辺縁系・前頭前野など情動・記憶に関与する領域に伝達される。
長期化によりこれらが亢進すると、末梢組織が回復していても痛みが生じる。
ゆえに、ただの質問は避けるか、質問しないという選択を検討する。
質問しないことがベスト(他職種への共有を含む)
最終的には質問しないという選択肢が、私の臨床では痛みの遷延を減らす結果につながってきた。
「痛いですか?」というただの質問は、感覚→知覚→認知・解釈→概念化→戦略計画→起動→回避行動のサイクルを回し、情動(不安・恐怖・怒り)・記憶に関与する大脳辺縁系・前頭前野を活性化させ、トップダウン痛へ移行しうる。
このサイクルを断つため、質問内容を精査し”ただの質問”の回数を減らし、最終的に質問しないことを目指す。
まとめ
・本稿の主眼は痛み評価の否定ではなく、無目的に反復されるただの質問の回避である。
・急性疼痛でADL・基本動作が阻害される場面では、構造化された痛み評価が最優先である。
・慢性疼痛/高リスクが示唆される場合は、質問設計と頻度を見直し、観察・行動指標を主軸とする。
・約2か月の可塑性を念頭に急性期管理で慢性化を防ぐ。
・チームで質問方針を共有し、漫然とした“痛み確認”の慣習を見直す。
●参考文献
1)田口敏彦他監修. 疼痛医学. 医学書院. 2020 年

・理学療法士
理学療法士免許取得後、関西の整形外科リハビリテーションクリニックへ勤務し、その後介護分野でのリハビリテーションに興味を持ち、宮﨑県のデイサービスに転職。現在はデイサービスの管理者をしながら自治体との介護予防事業なども行っている。
「介護施設をアミューズメントパークにする」というビジョンを持って介護と地域の境界線を曖昧に、かつ、効果あるリハビリテーションをいかに楽しく、利用者が能動的に行っていただけるかを考えながら臨床を行っている。
また、転倒予防に関しても興味があり、私自身臨床において身体機能だけでなく、認知機能、精神機能についてもアプローチを行う必要が大いにあると考えている。
そのために他職種との連携を図りながら転倒のリスクを限りなく減らせるよう日々臨床に取り組んでいる。

