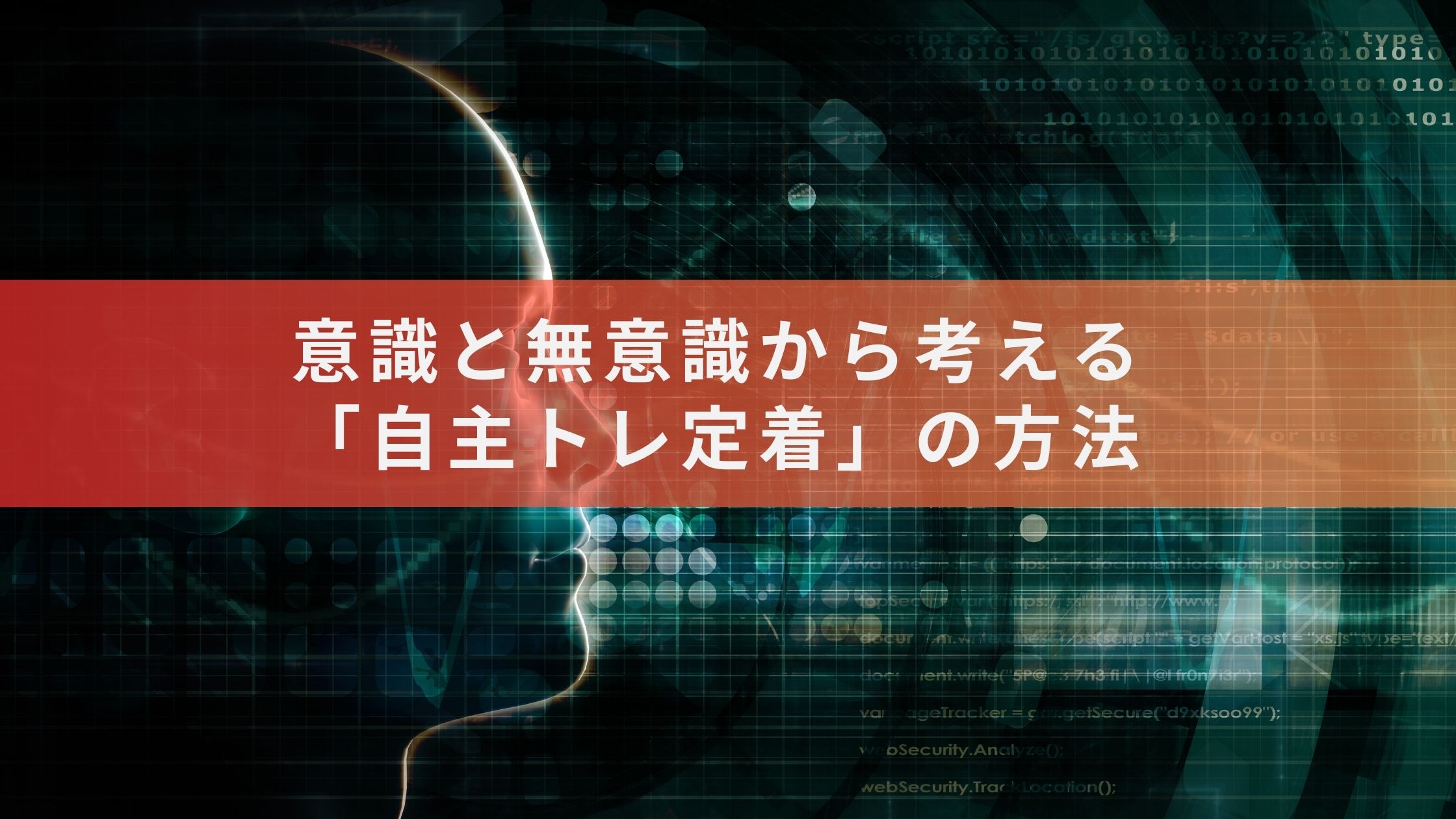はじめに
臨床で最も難しい課題の一つは、自主トレーニング(以下、自主トレ)を続けてもらうことである。
治療場面では実施できても、病棟や自宅の生活文脈では実施頻度が落ち、やがて消失することは少なくない。人の行動は大部分が無意識のルーティンにより構成されるとされ、日常の多くは“考えずに”進行する。
であるならば、自主トレも無意識の領域に落とし込むことが定着の近道となるはずである。
本稿では、意識/無意識の枠組みと「習慣化(インキュベート)の考え方」を踏まえ、若手療法士でも実装しやすい定着の設計図を提示する。
意識と無意識:ルーティンが行動を決める
私たちは歯磨きや着替え、通勤などを逐一「意識して」遂行してはいない。これは動作がルーティン化し、無意識下で実行されるレベルに達しているからである。
リハビリの文脈でも同様で、無意識に麻痺側が使える状態に近づくほど、使用頻度は自然と高まる。

臨床で着目すべきは、以下のような“無意識チェック”である。
・突発的な呼びかけに対し、どちらの手が反射的に伸びるか。
・物品の配置が取りにくい位置でも、麻痺側でつい手を出すか。
・日常場面での合目的的使用が、セラピストの指示なしに出現するか。
これらが陽性であれば、無意識化の進展が示唆される。
逆に陰性では、リハ室内の“意識的練習”が日常へ汎化していない可能性が高い。
インキュベートの法則:継続が無意識をつくる
新しい行動は、意識的な反復を経て無意識の回路に編み込まれる。
実務的には「約3週間の継続」が一つの目安として扱いやすい。
インキュベートの法則においては科学的根拠はないが、実際筆者の臨床感においても3週間継続できていれば習慣化できていく可能性が高くなると感じる。
重要なのは、何を・いつ・どこで・どれだけ行うかを具体化し、毎日同じ条件で行動を発火させることである。
これは脳の「きっかけ(トリガー)—行動—報酬」の連鎖を固定化する設計である。
臨床での工夫:無意識への橋渡し
・ 目標の具体化(When/Where/What/How much)
「〇回やってください」だけでは行動は立ち上がりにくい。以下のように詳細指定する。
・When(いつ):毎日16時に
・Where(どこで):リビングのこのテーブルで
・What(何を):麻痺側上肢のリーチ課題+巧緻課題
・How much(どれだけ):リーチ50回×3セット/ペグ操作3分×3セット
時間・場所を固定すると、環境そのものがトリガーとなり、患者は“考えずに”行動を起動しやすくなる。
・伴走と代替要員の手当て
本人一人では継続が難しい例は多い。
担当不在時に他職種(Ns、補助者)へ依頼し、同じ指示文で途切れなく伴走する体制を組む。これにより「今日はできなかった」を作らない。
・グループ自主トレの活用
最大3名程度での小集団実施は、相互モデリングと社会的促進をもたらす。
・同じ課題に取り組む仲間の存在は継続意欲を高める。
・成果の共有は、介入の意味づけを強化する。
“できた/届いた”のフィードバックが場で循環することが重要である。
・無意識チェックをタスク化する
「今日は突然ボールを差し出したとき、どちらの手が出たか」「トレー受け渡しで麻痺側を使ったか」など、突発課題を定期的に挿入する。指示反応ではなく、反射的選択を評価することで、無意識化の進度を可視化できる。
・ラポールと“快”の付与
ルーティン化には情動の色が乗る。
短時間でも「楽しい・心地よい」を介入に埋め込む。
例:好きな音楽に合わせた反復、成功体験を言語化して称賛、セット間の雑談など。
小さな快が「またやろう」を下支えする。
まとめ
自主トレの定着は、意識的反復を無意識化へ接続させる設計で決まる。
具体的な時間・場所・内容・量の固定、伴走体制、小集団の活用、突発課題による無意識チェックが要点である。
“継続が無意識を生む”という原則のもと、21日間の連続実施を一つの目安として設計し、生活へ汎化させる。
臨床のゴールは「リハ室でできること」を増やすことではない。
生活の中で“つい”起こる行動を設計し、患者自身の時間の流れに自主トレを溶け込ませることである。
以上が、意識と無意識の視点から見た自主トレ定着の実践知である。

・理学療法士
理学療法士免許取得後、関西の整形外科リハビリテーションクリニックへ勤務し、その後介護分野でのリハビリテーションに興味を持ち、宮﨑県のデイサービスに転職。現在はデイサービスの管理者をしながら自治体との介護予防事業なども行っている。
「介護施設をアミューズメントパークにする」というビジョンを持って介護と地域の境界線を曖昧に、かつ、効果あるリハビリテーションをいかに楽しく、利用者が能動的に行っていただけるかを考えながら臨床を行っている。
また、転倒予防に関しても興味があり、私自身臨床において身体機能だけでなく、認知機能、精神機能についてもアプローチを行う必要が大いにあると考えている。
そのために他職種との連携を図りながら転倒のリスクを限りなく減らせるよう日々臨床に取り組んでいる。